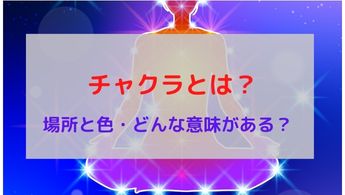護摩によって願いを叶えることができるのでしょうか?
願い事を書いた木を使って祈祷する護摩について調べてみました。
護摩とは何?
「護摩(ごま)」ってご存じですか?
山伏とか、修験者といわれる人が、不動明王の前に置かれた護摩壇(ごまだん)に護摩木を燃やしながら密教の秘法で、厄や災いを祓い、願いが成就するよう祈願します。
護摩堂のような小さな場所で行ったり、野外で大がかりにする大護摩もあります。
護摩行をすれば、どんな願いでも叶うわけではありません。
人の道に反れたものは、もちろん無理。
祈願をお願いする人の考え方やひととなり、その環境などを不動明王はみていらっしゃいます。
祈願をお願いしたから、何もしないのでは願いも叶いません(当然ですよね!)
その後の努力も必要です。
でも、それらをキチンとしていれば、本当にすごい願いも叶うのです。
古代からの秘法!護摩行の起源とは?
この護摩行ですが、起源は古代インドにあります。
紀元前1500年ごろ、当時のインドの神々への祈りの言葉を集めた聖典が編纂されました。
サンスクリット語で「リグ・グェーダ」と呼ばれます。
その中にアグニという火の神に捧げる儀式が載っており、加護を得るために「ホーマ」を行うとされます。
この「ホーマ」は火を焚きながら供物を捧げる儀式のことで、チベットから中国、日本に伝わる過程で「ホーマ」→「ゴマ(護摩)」になったといわれています。
さて、このアグニという火の神様、煩悩を焼き尽くし、邪悪なものから人間を守ってくれるといわれています。
日本の密教で行う護摩行では、護摩木=煩悩のシンボル火=智恵を表すとされています。
そして僧侶は護摩行で、息災、増益、調伏、敬愛の4種の法の成就を祈願するのです。
ちなみに調伏とは、煩悩や悪行に打ち勝つという意味です。
まさしく、古代インドの「ホーマ」と同じ意味ですね。
護摩行で、大願成就を祈ってみてはいかがですか?
護摩行を毎日しているお寺もあります。