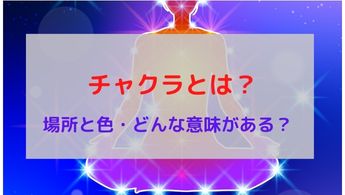干支は生まれ年を表すのに今でも使われています。
時代劇などでもご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、昔は干支で時間を呼んでいました。
十二支を使って時間を表す
生まれ年の表現の仕方のひとつに「干支」があります。
子(ねずみ)、丑(うし)、寅(とら)、
卯(うさぎ)、辰(たつ)、巳(へび・み)
午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、
酉(とり)、戌(いぬ)、亥(いのしし)
の12種類。だから十二支です(笑)。
2017年は酉年。
年賀状にニワトリの写真やイラストがあふれていました。
最近は年賀状の時しか登場しませんが(笑)、
昔は時刻を表すときにも
干支を使っていました。
23時~1時 子の刻
1時~3時 丑の刻
3時~5時 寅の刻
5時~7時 卯の刻
7時~9時 辰の刻
9時~11時 巳の刻
11時~13時 午の刻
13時~15時 未の刻
15時~17時 申の刻
17時~19時 酉の刻
19時~21時 戌の刻
21時~23時 亥の刻
時代劇で「辰の刻までに~」なんて、
時間を言い表すシーン、みたことありませんか?
午の刻に注目すると・・・
お昼の12時は午の刻の真ん中です。
ですから「正午」といいます。
また、午の刻の前が「午前」
午の刻の後ろが「午後」となのです。
面白いですね。
「魔」に逢う時刻は2つある
ひとつの干支で2時間ずつと表しますが、
これをさらに4つに分けます。
丑一つ・・・1時~1時30分
丑二つ・・・1時30分~2時
丑三つ・・・2時~2時30分
丑四つ・・・2時30分~3時
と、30分ずつに分けて時間を数えます。
そう、この丑三つが「丑三つ時」なのです。
「草木も眠る丑三つ時」の、「丑三つ時」!
丑の刻はあの世とつながる時間といわれており、
呪術などが行われる時間でもありました。
その中でも丑三つ時は
陰の気が充ち満ちる時。
このときに「丑の刻参り」といわれる
わら人形を五寸釘で打つという呪術を行ったそうです。
映画「君の名は」で一躍有名になった「黄昏時」。
夕暮れ時には辺りが暗くなり、夕日に照らされて
向こうにいる人がわかりにくくなる・・・そんな時間です。
「彼は誰?」→「誰そ彼?」→「たそがれ」→「黄昏」
になったといわれています。
黄昏時は夕方4時~6時ごろで、
「酉の刻」にあたります。
この時間は「逢魔ヶ時(おうまがどき)」といわれ
魔物に遭遇する、大きな災いに遭うという時間でした。
太陽のある昼と太陽のない夜とが
切り替わるポイントとなる時間帯です。
現在でも車などで事故が起こりやすい時間帯といわれていますよね。
このように現代でも年を表すだけではなく、
干支は日常生活に深くかかわっています。